西風恋慕
ーー美しさは、凶器だ。
その艶で、その容貌で
心の核をいとも簡単に破壊してしまうのだから。
美しさを知らなければ、
自分の心の醜さに気がつくこともなかったのに。
俺の物語は、1人の孤独な少年を中心に展開されていく。
物憂げで、寂しそうに。雪のように白い手と夜闇のように黒い髪が特徴的な彼。伏し目がちなせいか、まつ毛が影を落としている。
少年は手を止めた。彼の手に握られているのは、この地には珍しい藤の花だった。藤の花を焦がすように注がれていた視線が俺に向かう。
焼き焦がすというより、俺の中で血液がゆっくりと沸騰していくような感覚が生まれた。
ーあぁ。美しい瞳だ。
熱を宿すような、唐紅に彩られた紅い瞳。
大きくひみらかれたその瞳に俺は吸い込まれそうになる。
彼の目に、俺はどう写っているのだろう。
きっとすでに、初対面で無遠慮に他人を観察するおかしな人物だと脳が登録してしまっているのだろう。
けれどこの時はどうしてか、激しい衝動が襲ってきていた。
ー声が聞きたい。話したい。
ただ相手を求めるだけの小さな願い。欲。
自分の情報の開示など考えてもいない。
知りたい。知りたい。知りたい。
ー君はなぜ、悲しそうに花を見つめているのか。
その視線の理由を聞きたい。誰かとの思い出を思い出す引き金になっているのだろうか。
それは君の大事な人なのか。
悲しませている相手を想い、美しい君は美を形容するための花を見つめて何を想っているのだろうか。
ー君の名前はなんていうのか。
ー歳はいくつだろう。俺と近そうにも見える。そうなら話が合うかもしれない。
ー藤の花の別称は忘れたけれど、たしか春頃に咲く花だった。ここでは花屋以外で見ないから珍しく思ったんだが、どこかで摘んできたのか。
ー家族に兄弟はいるのか。俺は上に1人いる。兄と俺はあまり似ていないが。
質問が浮かんでは消え、浮かんでは消えを繰り返す。
浮かんだものは口から出ていくこともなく、次々に浮かび上がる質問にかき消されていく。
やがて君は、呆然とする俺に向かって言った。
「もしかして、俺を迎えに来たんですか?」
男である君は、鈴の音のような声で初めて俺に向けて言葉を発した。
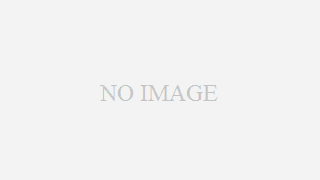 BLove[ビーラブ]
BLove[ビーラブ]